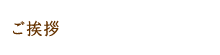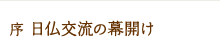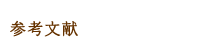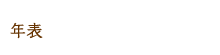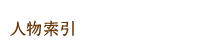![]()
4. 『昆虫記』をめぐる人びと
アンリ・ファーブル(1823-1915)の『昆虫記』は、本国フランスよりも日本においてはるかに知名度が高い。大正8(1919)年、日本にファーブルを最初に紹介したのは、キリスト教社会運動家の賀川豊彦(1888-1960)であった。その後、同11(1922)年から無政府主義者の大杉栄(1885-1923)が『昆虫記』の全訳刊行に取り組む。明治の論壇においては、加藤弘之(1836-1916)、丘浅次郎(1868-1944)らによる進化論の紹介が盛んであったが、大正期に登場した賀川、大杉らはピョートル・クロポトキン(1842-1921)の『相互扶助論』の影響の下、その生存競争説に批判的であった。大杉による翻訳は、ファーブルが生き生きと描き出す昆虫の本能の中に相互扶助の姿を見出し、資本主義社会における競争原理を批判する側面があった。『昆虫記』の翻訳者には、マルセル・モース(1872-1950)に学んだきだみのる(山田吉彦1895-1975)など、近代社会と個人の関係を考察した思想家が多い。
フアブル(大杉栄・椎名其二訳)『昆虫記』叢文閣,大正11-15(1922-1926)【385-207】
大杉は軍人家庭に育ち、陸軍幼年学校に入るが、級友との格闘が元で退学処分となった。その後、東京外国語学校(現東京外国語大学)の仏語科に入学、谷中村事件を機に『平民新聞』【WB43-71】の幸徳秋水(1871-1911)らを訪ね、社会運動の世界に入った。大逆事件で幸徳らが処刑されると、その後の運動を中心で担った。「一犯一語」を掲げ、収監のたびに新たな言語を習得し、翻訳・執筆で生活の資を得た。大正8(1919)年、尾行巡査殴打事件で豊多摩監獄収監中に『昆虫記』の英語抄訳版を読み、翻訳を決意した。底本には、同年刊の仏語原書(絵入版)を用い、叢文閣から刊行された。訳者序において大杉は、ファーブルによるヒジリタマオシコガネ(ふんころがし)の観察に「其の徹底的糞虫さ加減!」と感嘆しているが、個性と自由を重視し、「生の拡充」を唱えた自らの主義に通じるものを感じたのであろうか。大杉には、他にチャールズ・ダーウィン(1809-1882)の『種の起原』の翻訳もある。
大杉栄『日本脱出記』アルス,大正12(1923)【514-185】
大正11(1922)年、大杉は翌年ベルリンで開催される予定の国際無政府主義大会に出席するため、偽造旅券を用いて上海経由でフランスへ渡り、パリの労働者街に起居した。大杉の見た当時のパリは、下宿に電灯やトイレもなく、都市生活の快適さという面では日本が上回っていたようである。翌年5月、メーデーで飛び入り演説したのをきっかけに逮捕され、ラ・サンテ監獄に拘留、強制送還された。本書は、この体験を綴ったもので、同年9月に関東大震災後の甘粕事件で、伊藤野枝(1895-1923)とともに虐殺された大杉の遺著となった。版元のアルスは、北原白秋(1885-1942)の弟鉄雄(1887-1957)が経営し、美しい造本で知られた。本書の見返しには、フランス政府発行の強制送還命令書が印刷され、長女魔子(1917-1968)を抱く大杉の写真が口絵に掲げられている。本書中には、「魔子よ、魔子/パパは今/世界に名高い/パリの牢やラ・サンテに。」で始まる詩も載せられている。
ヂェ・ヴェ・ルグロ(椎名其二訳)『科学の詩人』叢文閣, 大正14(1925)【544-128】
大杉の死後、叢文閣版『昆虫記』の翻訳は、椎名其二(1887-1962)に引き継がれた。椎名は当時、フランス人の妻と子を連れて帰国し、早稲田大学で教鞭をとっていた。石川三四郎(1876-1956)らと親交があり、無政府主義に近い思想の持ち主であった。昭和2(1927)年再度フランスに渡り、ドイツ占領下にはレジスタンスに協力、同37(1962)年パリで死去。
本書は、ファーブルの生前に弟子ジョルジュ・ルグロ(1862-?)が編んだ伝記である。南仏の寒村に生まれたファーブルは、学校教師の傍ら、独学で数学と博物学を学んだ。生きた昆虫の生態を観察するその研究方法は、当時としては斬新なもので正確を極めたが、学界には容れられず困窮の中研究を続けた。進化論については、観察から得られないとして終生認めなかったが、ダーウィンはファーブルを偉大な観察者として称えた。ジュディット・ゴーチエの「トンボの国」日本において、『昆虫記』は熱烈な読者を得ることとなった。

ファーブル(林達夫・山田吉彦訳)『昆虫記』岩波書店,昭和5-33(1930-1958)【569-14】
『昆虫記』全訳として最も版を重ねる岩波文庫版は、林達夫(1896-1984)と山田吉彦の第二次世界大戦を挟み30年近くにもわたる訳業である。林の名はリベラルな百科全書的知識人として知られるが、山田吉彦とは誰か。山田は、戦後「きだみのる」のペンネームで知られた作家である。フランス語学校アテネ・フランセの創立者ジョゼフ・コット(1875-1949)に養育され、昭和9(1934)年フランス政府給費留学生としてパリに留学、マルセル・モースの下で人類学を研究した。同門に芸術家の岡本太郎(1911-1996)がいる。帰国後に住んだ東京・八王子の寒村をフィールドに、日本文化の根底を探る論考を発表し注目された。きだとの出会いを林は、「この奇怪な魅力に富んだ紳士との付合いのはじまりであり、たちまちにして岩波文庫版『昆虫記』に、ぼくも名を連ねて、その翻訳の片棒をかつぐ羽目に陥ったのであった。それ以来三十年、彼との悪縁良縁、そしてファーブルとの悪縁良縁はえんえんと続く」と述べている。

きだ・みのる『道徳を否む者』新潮社,1955【913.6-Y226d】
きだが師コットの死をきっかけに、半生を回想した自伝的小説。奄美大島で医師の家庭に生まれ、父の赴任先であった台湾キールンに移住、同地の過酷な生活で体調を崩したきだは、東京へ転校を余儀なくされた。寄宿先の叔父の家で疎まれ、死を決意して東京湾に身を投げるが果たせず、救いを求めて訪れた北海道のトラピスト修道院で、同様に東京帝大における処遇に悩み滞在していたコットの知遇を得た。以後、コットの養育を受けたきだの心身は、日本人離れした発達を見せ、大学を辞したコットが設立したアテネ・フランセで初め事務員として、後には教師として働いた。やがて39歳で民間から異例のフランス政府給費留学生に選ばれた。帰国の船上、関門海峡から望んだ日本の風景に惹きつけられたことを本書で語っているが、15年後に加藤周一(1919-2008)が同様の体験をすることとなる(1950年代頃まで航路が用いられた)。きだの関心は、日本社会の基底構造へと向けられていく。